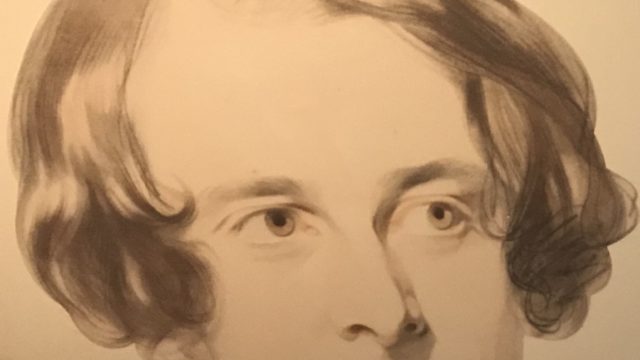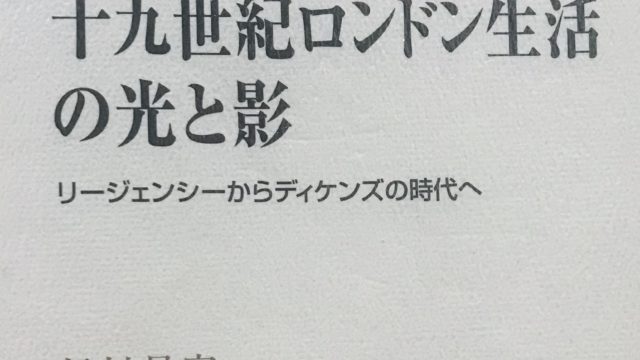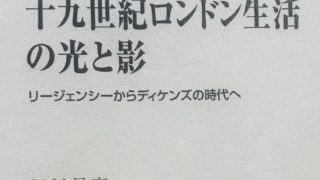そう、私は泣いていました―でも、幽霊の話のせいではありませんでした。
「窓をたたく音」ダイナ・マロック
『ヴィクトリア朝幽霊物語』松岡光治編訳 アティーナ・プレス
今回も『ヴィクトリア朝幽霊物語』から短編を一作。
こちらは残念ながら絶版、しかし、あとがき含む全文がPDFで無料公開となっている。
松岡光治編訳『ヴィクトリア朝幽霊物語(短篇集)』(アティーナ・プレス、文庫版、2013年3月)
これまでの記事はこちら。
イギリスの幽霊物語が好きだ/「約束を守った花婿」イーディス・ネズビット『ヴィクトリア朝幽霊物語』(アティーナ・プレス) – ディケンズと好きの片隅
恐怖しない語り手/「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ – ディケンズと好きの片隅
今回取り上げるのは、ダイナ・マロックの「窓をたたく音」。
1856年8月号の『フレイザーズ・マガジン』初出。
作品の表紙に使われている写真は『嵐が丘』の亡霊となって窓をたたくキャサリンを思わせ、ぞっとさせるが、作品はただ怖いだけの幽霊物語ではない。
作品の内容にふれています。
老婦人の語る幽霊物語。まだ若い女性の語り手が聞き役となる。
幽霊の話をしながら、ついつい違う話に脱線してしまう75歳のドロシーおばあちゃんが愛らしく、だからこそ、この後の展開が切ない。
聴き手の「わたし」による、
私は幽霊をほとんど信じていません。幽霊なんか有害無益だからです。(48)
という語りからこの作品は始まるが、そう言う彼女が「唯一本当に完璧な幽霊物語だと思える話」をする、として話すのがドロシーおばあちゃんの幽霊物語である。
ドロシーが、ずっと昔、自分がまだ18歳の時に恋をしていたのだ、と告げると、若かった聴き手の「わたし」は、当然その相手がおばあちゃんの夫のマッカッサー氏だと思いこみ、それを口にしてしまう。
しかし、その相手というのは現在の夫のマッカッサー氏ではなく、エヴァレスト氏であった。
両親とともにバースからロンドンにやってきたドロシーは、ロンドンでエヴァレストと過ごす時間を何よりも幸せに感じていた。
しかし、ドルリー・レーン劇場で『ハムレット』を観るのを楽しみにしていたにも関わらず、出産間近だった母親は故郷に戻ると言い出す。愛する人との別れを悲しんだドロシーは、母親を一人帰らせるというエヴァレストの提案に乗ってしまう。
ドルリー・レーン劇場でジョセフ・グリマルディの出演する『ハムレット』を楽しんだ夜、ドロシーが女中のパティーとおしゃべりをしていると、突然窓をたたく音がする。それは、人間の指が窓をたたくような音だった。別室にいた父親は夜中うなされ、翌朝、すぐに帰郷すると告げる。しかし、別れを惜しむ恋人同士の二人は、せめて夕方までその時間を引き伸ばしたいと思い、その説得をエヴァレストが行う。彼は、ドロシーの父親が聴いた音や目にした幽霊は、夕べ『ハムレット』を観たことによって影響された幻に過ぎないと一笑する。説得のかいあって、父親は出発を遅らせ、恋人たちは彼らの時間をもうしばらく持つことができたのだが…。
この出来事がドロシーの一生の悔いとなった理由は二つある。
一つは、まさにドロシーが窓をたたく音を聞き、父親が赤ん坊を抱いた妻の幽霊を見たその時に、彼女は出産で亡くなっていたから。
そしてもう一つは、そのことがあってから父親はエヴァレストに偏見を持つようになり、二人の仲が裂かれてしまったから。
二人はその後二十年間は会うことはなかったという。
数年してエヴァレストは別の女性と結婚し、ドロシーも31歳の時にマッカッサー氏と結婚した。
しかし、この物語の切なさはこの後のドロシーのセリフにある。
「ですから、私たちはどちらも不幸だったわけではありません。少なくとも、たいていの人たちと同じように幸せでした。そのあと、私たちは互いに心の友となりました。エヴァレスト夫妻は私に会いに来てくださいますよ、日曜日はほとんど毎週のようにね。まあ、お馬鹿さんね、泣いているの?」(72)
この話は幽霊物語であると同時に失った恋の物語である。
今でも毎週夫妻が訪ねてくる、というドロシーの言葉が、過去のことは過去のことと穏やかに消化しているようでありながらも切ない。
その後、記事の冒頭で引用した語り手の言葉でこの物語は締めくくられるのだが、読んでいて語り手と同じ気持ちになって胸を締め付けられた。誰も悪いわけじゃない。ただただ不運が重なったのだ。
作中で言及されるジェセフ・グリマルディ(1778-1837)は解説にもあるが、ディケンズが大ファンだった道化役者。ドロシーの半世紀以上前の回想の中で、彼の姿はドルリー・レーン劇場で全盛期の輝きを放っている。
この作品を読んで、エリザベス・ギャスケルの『クランフォード』を思い出した。
一見するとほんわかおっとりした、どこにでもいるような年配の女性たちの心には、様々なつらい過去や記憶がある。だけどそれを穏やかに、時には涙を流しながらも、前向きに生きていこうとする女性たちに対する人間賛歌。そんな風にも読み取れた。
老年の女性と聞き役の若い女性との間にある信頼関係が作品のあたたかさを生み出している点も共通している。
マロックもギャスケルも共にヴィクトリア朝に活躍した女性作家。
普段ヴィクトリア朝の男性作家の作品を読むことの多い私にはどちらも新鮮で深く突き刺さる大切な作品となった。
切ないけれど読後感のよいヴィクトリア朝幽霊物語を読みたい人にはおすすめの一作。