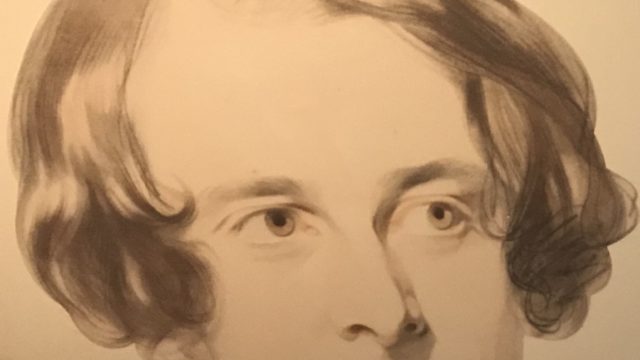ぼくはやっとマットを―ぼくが愛して、憎んで、殺してしまった親友を―永久に失ったことに気づいた。
「鉄道員の復讐」アミーリア・エドワーズ
『ヴィクトリア朝幽霊物語』松岡光治編訳 アティーナ・プレス
『ヴィクトリア朝幽霊物語』から短編を一作紹介。
こちらは残念ながら絶版、しかし、あとがき含む全文がPDFで無料公開となっている。
松岡光治編訳『ヴィクトリア朝幽霊物語(短篇集)』(アティーナ・プレス、文庫版、2013年3月)
これまでの記事はこちら。
イギリスの幽霊物語が好きだ/「約束を守った花婿」イーディス・ネズビット『ヴィクトリア朝幽霊物語』(アティーナ・プレス) – ディケンズと好きの片隅
恐怖しない語り手/「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ – ディケンズと好きの片隅
老婦人の語る幽霊物語/「窓をたたく音」ダイナ・マロック – ディケンズと好きの片隅
四作目はアミーリア・エドワーズ(1831-1892)による「鉄道員の復讐」。
ディケンズ編集の雑誌『オール・ザ・イヤー・ラウンド』の1866年クリスマス特集号に掲載された作品。原題は”No.5 Branch Line: The Engineer”。
扉絵には作品中に言及されるティツィアーノの『鏡を見る女』が使われている。
作品の内容にふれています。
まずはじめに、この作品における幽霊は恐怖というより、救いである。
むしろ、生きている人間の嫉妬や恨みの感情が恐ろしく、物語終盤で語り手の巻き添えを食らう火夫の表情にもその恐怖が読み取れる。
ベンジャミン・ハーディとマシュー・プライスは同じ村で育った子供の頃からの親友だ。バーミンガムで職を得た二人は仕事で訪れたイタリアの素晴らしさに心を打たれ、ジェノヴァに移り住むことを決める。しかし、下宿先の魅力的なジアネッタに恋をしたことから二人の友情が壊れ始める…。
物語は冒頭のイギリスの村の牧歌的な雰囲気から一変し、イタリアでの一人の女性をめぐる事件へと発展する。嫉妬と疑念に狂ったベンジャミンはマシューをナイフで刺し、その傷が原因でマシューは亡くなる。
二人はイギリス人だが、ここでの諍いや、その後刺した男が刺された男を誰より献身的に看病するところなど、E.M.フォースターの『眺めのいい部屋』で主人公ルーシーたちが目撃した殺人事件を起こしたイタリア人の様子を彷彿とさせる。
この作品の一貫した恐ろしさは語り手ベンジャミン・ハーディの性格である。一人称による彼の語りでは、自身と親友マシューを翻弄する残酷な女性としてジアネッタに苛烈な愛憎の念を一方的に募らせる。
それは彼の過失ではない。誠実で心やさしい男だったから、そんな事態を自ら進んで引き起こすようなことはなかった。それはぼくが―確かに激しやすい性格であったが―悪かったからだとも思わない。最初から最後まで、すべては―罪も恥も悲しみも―彼女のせいだったのである。(85)
美人で人気者のジアネッタが、ベンジャミンやマシューを相手に選ばなければいけない理由はどこにもないが、ベンジャミンは自分か彼のどちらかを誠実に選べとジアネッタに迫る。ジアネッタが気の多い女性だったとしても、彼女の人生の選択権は彼女にあるべきだ。しかし、ベンジャミンは自分の気持ちを優先するばかりで、ジアネッタの気持ちを慮ることはない。一方、恋敵である親友マットに対して歪んだ愛情を抱いている。
ぼくは自分自身に問いかけてみた―マットにとってのぼく、ぼくにとってのマットほどに価値のある女性が、この世にはたしているだろうか、と。(86)
ベンジャミンは明らかに女性嫌悪、女性恐怖の男性として書かれており、ジアネッタを自分を翻弄する残酷な「運命の女」に仕立てて彼女に憎しみを向ける。 その結果、親友を死に追いやることになる傷害事件を引き起こす。
一人の女性をめぐる三角関係でありながら、恋敵であるマットに同じように、いや、それ以上に愛情を傾ける様子は、ホモソーシャルな関係と読み取れるが、ここでは、作者が女性であることに留意する必要があるだろう。
語り手のもう一つの不気味さはその冷静さである。
もちろん回想の形で語っているので、時間の経過などが自身の経験を客観視させているという面もあるだろうが、語り手の中にある激しやすい兆候が語りにはあまり滲んでいないところが恐ろしさを感じさせる。
年月が経っても心を穏やかにすることはなかったという心理の描き方は鋭い。
彼はきっと今でもジアネッタを許してなどいないのだろう。たとえ彼女にそれだけの罪がなかったとしても。
後にエジプト調査基金を設立することになるアミーリア・エドワーズ。彼女の他の作品が読みたくなった。
屈折した心理を巧みに描いたヴィクトリア朝幽霊小説を求める人におすすめの一作。